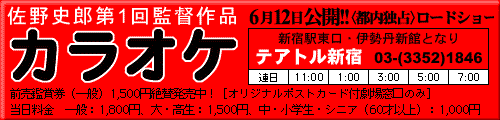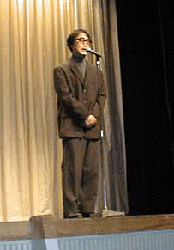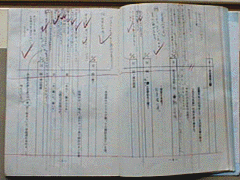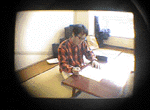『カラオケ』マスコミ試写を終えて  1999/4/18
番組で楽屋がいっしょになった伊東四朗さんなんかも細かくギャグを観てくださってたね。ノリで作ったものじゃないからね。 取材を受けても、カラオケ・ボックスに入ってからは「アッという間だった」とか、だいたい評判がいいね。 それに細かく演出をつけた人が「そのままじゃない」とか「自然に見えた」とか言われると、演出家としては嬉しいよね。 俳優として細かく作って「地で演ってんじゃないの」とか「そのままじゃん」と言われることはあっても、演出したことはないから役者だけをやってると味わえない感覚だよね。 この監督用の台本を見ると、たくさんのメモやスケッチが書かれているけど、これは自分のイメージをはっきりさせたいから? それとも他のスタッフに伝えやすいから?
プレス試写でどんな反応なんだろうなって心配だったんだけど、思った以上に伝わっている実感があるね。 けっこう笑いも起きていたし、音楽も軽妙で重たくなりがちな画面を軽やかにしてたね。
カラオケ・ボックスに入ってからは筒美京平オンパレードだから、その力も強かったね。
ちょうど、筒美京平再評価のブームもあるし。
カルトGS、モンド、ラウンジと、去年撮っている時にひたひたと追い風のように来ていたからね。だからといって、おしゃれな映画にはしたくないというより、出来ないからね。 公開されたらこのHPにも感想がくるだろうから、それが楽しみだね。
そうそう、タルコフスキーの評論を専門にやってる人に取材を受けたんだけど、細かいカット割りを分析をやられて参ったけどね。日本映画における「カラオケ」のカット割り、音の使い方、タイミングとか編集の仕方とかの違いを延々と分析してくれた。(笑) 全部が全部、理屈で作ってるわけでもないだろうし、そんなタイプでもないものね。
たとえば、警報器とシャッターに一瞬恵子ちゃんの顔が映しだされるのだって、説明しようと思えば出来るけど、感覚的なものでもあるしね。でも緊迫感は出るのは間違いないからね。 |
『カラオケ』の出来るまで  1999/4/18 じゃあ、中学校の同窓会をモチーフにするというアイディアもまだなかったと。
そう、そう。
同窓会 第22期卒業生 佐野史郎
それと、「カラオケ」のシーンで同窓生が割烹に集まるところがあるんだけど、美保純さんに旦那のベンガルから電話がかかってきて、フスマ一枚隔ててみんなが喋ってるというところで、現場で台詞を急遽書いたんだよね。
「カラオケ」S77用Off台詞 S78に続く。 |
★映画監督デビュー作品『カラオケ』を語る はこちらへ